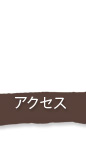第89回 「なぜ、10億人も飢えている人がいるのだろうか?」
気持ちの良い秋晴れの一日。今回は興学院のガラス戸にスクリーンを張り、商店街の路上に机とイスを並べて開催。久々にオリジナルの姿での中崎北天満サイエンスカフェとなりました。路上でやっていることから、買い物途中のお母さんや試合帰りの野球少年も足を止めて話を聞いていってくれます。この日、すぐ近くの扇町公園では「北区民カーニバル」。そして、こちら、おいでやす通りでは恒例のサイエンスカフェ。地域はイベントづくしの一日になりました。
 話題提供者の上須道徳さんは、経済学を専門として、環境問題や発展途上国の開発をテーマに研究をされています。そして、今人類が直面している地球規模の課題の一つ「食糧問題」について、様々なデータをもとに経済学的な観点から話をされました。
世界の中で、10億人もごはんを食べられない人たちがいると聞くと「それは地球上で生産できる食糧が十分ではないからだ」と思いますよね。でも現実は違うと上須さん。
確かに世界の人口はどんどん増加して行き、現在2015年には72億人を突破、半世紀で2倍に。一方で、穀物を作る土地は増えておらず、ずっと横ばいのままです。しかし、品種改良、化学肥料の投入などの農業技術の発達と、産業化によって、穀物生産効率は人口の伸びと同じくらい上昇しつづけました。その結果、カロリーベースでは、1960年代以降、世界中の人口を養うだけの穀物生産があったとされています。しかしそれでも10億人もの人が「飢えている」という現状が目の前に存在しています。それはなぜでしょうか。
食糧問題は単に食料の生産だけではなく、食べ物へのアクセスが深く関わっています。つまり、食糧問題=貧困問題と言い換えても過言ではありません。貧困状態にある人は食べ物を買えず、また食べられなければ元気も希望も無くなってしまいます。この負のスパイラルに加えて、穀物の価格は世界規模の市場で決定され、投機などで価格の上昇が起きたときには、真っ先に経済力の弱い人たちにしわ寄せが来てしまうのです。最近「バイオ燃料」にも大量の穀物が使われており、人と車が穀物を奪い合うというおかしな状況が生まれているのも事実です。
話題提供者の上須道徳さんは、経済学を専門として、環境問題や発展途上国の開発をテーマに研究をされています。そして、今人類が直面している地球規模の課題の一つ「食糧問題」について、様々なデータをもとに経済学的な観点から話をされました。
世界の中で、10億人もごはんを食べられない人たちがいると聞くと「それは地球上で生産できる食糧が十分ではないからだ」と思いますよね。でも現実は違うと上須さん。
確かに世界の人口はどんどん増加して行き、現在2015年には72億人を突破、半世紀で2倍に。一方で、穀物を作る土地は増えておらず、ずっと横ばいのままです。しかし、品種改良、化学肥料の投入などの農業技術の発達と、産業化によって、穀物生産効率は人口の伸びと同じくらい上昇しつづけました。その結果、カロリーベースでは、1960年代以降、世界中の人口を養うだけの穀物生産があったとされています。しかしそれでも10億人もの人が「飢えている」という現状が目の前に存在しています。それはなぜでしょうか。
食糧問題は単に食料の生産だけではなく、食べ物へのアクセスが深く関わっています。つまり、食糧問題=貧困問題と言い換えても過言ではありません。貧困状態にある人は食べ物を買えず、また食べられなければ元気も希望も無くなってしまいます。この負のスパイラルに加えて、穀物の価格は世界規模の市場で決定され、投機などで価格の上昇が起きたときには、真っ先に経済力の弱い人たちにしわ寄せが来てしまうのです。最近「バイオ燃料」にも大量の穀物が使われており、人と車が穀物を奪い合うというおかしな状況が生まれているのも事実です。
 また、産業化された農業は環境に対する負荷が大きく、地球温暖化の原因にもなっていると言います。牛などの反芻動物のゲップや水田の泥から放出されるメタンは、二酸化炭素の約30倍もの温室効果があり、化学肥料の使用で生じる二酸化窒素も同様に温室効果ガスです。また、綿花栽培のために、「アラル海の悲劇」で知られるように、大きな湖が数十年で干からびてしまうこともあります。
このほかにも、食に関しての考えるべきテーマは数多くあります。食糧の貿易のルール、食の安全の問題、食糧のサプライチェーン(スーパーマーケット・ファーストフードチェーンの影響)、食料廃棄問題、Land rush(食料供給のための農地買占め)・・・。そして、足元の日本に目を向けてみると、耕作放棄地、後継者不足、食糧の海外依存といったようにたくさんの課題があります。
今回のサイエンスカフェは、我々の生活に関わっても、少し知ってみるだけで「見過ごしてはいられない!」と思わせてくれるようなたくさんの課題があることに気づかせてくれました。上須さんは最後に、「人間が抱える最も悪いことは“無関心”であり、それは科学の力ではどうしようもできないことである」というヘレンケラーの名言を紹介して話を終えました。
今回の話題のように、確立された解決策がなく、これから私たちが意図的に考え続けて行かなければならないテーマは数えきれません。難しく混乱してしまうような課題を一部の研究者や専門家に任せるのではなく、私たち市民が主体性を持って物事を考えるようにしたいものです。これからも参加者が何かを持ち帰ることができるようなサイエンスカフェにしていきたいと思いました。(S. T.)
また、産業化された農業は環境に対する負荷が大きく、地球温暖化の原因にもなっていると言います。牛などの反芻動物のゲップや水田の泥から放出されるメタンは、二酸化炭素の約30倍もの温室効果があり、化学肥料の使用で生じる二酸化窒素も同様に温室効果ガスです。また、綿花栽培のために、「アラル海の悲劇」で知られるように、大きな湖が数十年で干からびてしまうこともあります。
このほかにも、食に関しての考えるべきテーマは数多くあります。食糧の貿易のルール、食の安全の問題、食糧のサプライチェーン(スーパーマーケット・ファーストフードチェーンの影響)、食料廃棄問題、Land rush(食料供給のための農地買占め)・・・。そして、足元の日本に目を向けてみると、耕作放棄地、後継者不足、食糧の海外依存といったようにたくさんの課題があります。
今回のサイエンスカフェは、我々の生活に関わっても、少し知ってみるだけで「見過ごしてはいられない!」と思わせてくれるようなたくさんの課題があることに気づかせてくれました。上須さんは最後に、「人間が抱える最も悪いことは“無関心”であり、それは科学の力ではどうしようもできないことである」というヘレンケラーの名言を紹介して話を終えました。
今回の話題のように、確立された解決策がなく、これから私たちが意図的に考え続けて行かなければならないテーマは数えきれません。難しく混乱してしまうような課題を一部の研究者や専門家に任せるのではなく、私たち市民が主体性を持って物事を考えるようにしたいものです。これからも参加者が何かを持ち帰ることができるようなサイエンスカフェにしていきたいと思いました。(S. T.)
第88回 「特殊環境における運動と栄養」
今回の中崎北天満サイエンスカフェは、大阪マラソン応援企画ということで、5年連続となる渡邊完児さんの話題提供です。渡邊さん、今年は大阪マラソンに参加登録でできたとのことです。快走・完走されることを期待しましょう。渡邊さんはスポーツ関わる栄養学が専門なのですが、今年は、子供や老人の熱中症による事故が問題になることも多いことから、高温などの厳しい環境で活動する時の水分や栄養のとり方を解説していただきました。
 「特殊環境における運動と栄養」という題目に、果たしてどれくらいの参加者があるのかと、主催者ですら半信半疑でしたが、ちゃんと参加者があって、いつものようににぎやかに始まりました。
「特殊環境における運動と栄養」という題目に、果たしてどれくらいの参加者があるのかと、主催者ですら半信半疑でしたが、ちゃんと参加者があって、いつものようににぎやかに始まりました。
私たちは日常的に、いろいろのストレスにさらされて生活しています。運動するのも、自分で積極的に体にストレスをかけていると考えることができます。人間の体はストレスの強度に応じて、初期には警告反応を示し、やがてストレスに抵抗するようになります。ストレスはその程度が問題で、適度な大きさであれば回復することができますが、適応限界を超えてしまうと回復が困難になります。
ストレス下においては、体にエネルギー代謝が促進されると同時に、ビタミンE,C,ベータカロチンなどの抗酸化物質やたんぱく質が不足気味になります。しかし、過度のストレスでない限り、日常の規則正しい食事で十分に補充されます。
 脳の視床下部には、体温調節の中枢があって、暑さ寒さのストレスに体は対処してくれます。ところが、最近ではどこの家庭でもエアコンを使っているので、体がこれらのストレスをあまり感じることのないまま生活をしています。その結果、私たちの体温調節能力が弱まっているそうです。エアコンの温度設定に、エコ・省エネが言われますが、経済のためではなく、自分の適応能力を高めることも意識すべきだと渡邊さん。
脳の視床下部には、体温調節の中枢があって、暑さ寒さのストレスに体は対処してくれます。ところが、最近ではどこの家庭でもエアコンを使っているので、体がこれらのストレスをあまり感じることのないまま生活をしています。その結果、私たちの体温調節能力が弱まっているそうです。エアコンの温度設定に、エコ・省エネが言われますが、経済のためではなく、自分の適応能力を高めることも意識すべきだと渡邊さん。
しかし、熱中症は場合によっては死に至ることもあるので、きちんと対処法を知っておくことが必要。熱中症には、熱けいれん(発汗でミネラルが不足)、熱疲はい(水分不足)、熱射病の3つがあり、前の2つは「運動前から」ミネラルウオーターを補給することで予防できます。熱射病のときは体温調整能力が失われているので、足を高くして、首筋や脇の下、大腿部を急いで冷やす必要があります。
特殊環境と言えば、宇宙ステーションの無重力状態もその1つ。無重力状態をシミュレーションするために、実際に寝たきりでの生活で実験するそうです。宇宙飛行士が宇宙で生活を続けると、尿中のカルシウム濃度が高くなり、骨からカルシウムが抜けてゆくことが分かります。地上では、骨は常に重力に抗して体を支えているのに、宇宙空間ではその必要がなくなるので、途端に骨は脆くなってゆきます。骨には、破骨細胞と骨芽細胞があって、骨量が管理されていますが、歳を取るごとに破骨細胞の方が優勢になり、骨粗しょう症の原因にもなります。無重力実験の経験から、適度の運動の刺激(ストレス)で、骨芽細胞を活性化させることが、これを防ぐことに役立つと考えられます。
やはり楽をすることばかりを考えないで、自分の体が要求していることも意識して生活することが大切ですね。(Y. N.)